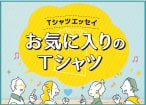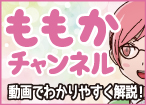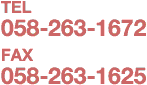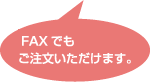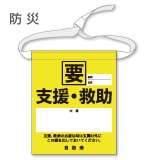ビブス(ゼッケン)の名前の由来
みなさんが日常のいたるところで目にするビブス(ゼッケン)。
これは、スポーツなどで競技者の衣服の前後につける番号を記したアイテムを指していますが、国際的な場面では、一般的に”ビブス”と呼ばれることが多いようです。
当サイトでは、どちらでもわかりやすいよう”ビブス(ゼッケン)”という表示にしています。
これってもともと何語なんだろう。pecheスタッフが何気なく感じた疑問を解決すべく、ちょっと調べてみました。
ビブスの語源は英語
ビブスの語源は明確です。辞書で引くと、《bib(よだれ掛け・胸当て)の複数形》と出てきます。
ゼッケンの語源は諸説ある
ゼッケンの語源は諸説あるようで、どれも決定打に欠けているのが現状です。
1.元々は、番号票と呼ばれていた!?
明治44年11月18日・19日、羽田運動場で行われた陸上競技オリンピック予備会の審判及び協議規定第四には、ゼッケンのことを”番号票”と記されています。 そのことから、当時日本では番号票と呼んでいたのではないかと予想されます。
2.ドイツ語由来説
明治45年の陸軍スキー演習の日誌の中に、初めて”ゼッケン”という言葉が出てきます。この時の演習の教官は、オーストリア=ハンガリー帝国の軍人であり、日本で初めて本格的なスキー指導をおこなったテオドール・エードラー・フォン・レルヒ(通称レルヒ少佐)。
レルヒ少佐のドイツ語の発音のsackchen(小麦粉を入れる袋)が日本語ではゼッケンと聞こえ、定着したとする説があります。

▲レルヒ少佐肖像
3.その他の諸説
他にも、下に挙げたような様々な説があり、これといった定説がないのが現状です。
・イタリア語のzecckinoという金貨の模様を馬の腹の布に書いて所有者を明らかにしていたという風習による説
(新修体育大辞典(1976)
・ラテン語のsequentiaから派生したとする説
・ドイツ語のSequensから派生したとする説
・ノルウェー語から派生したとする説
※参考文献「レルヒ来日前後を中心として」野沢巌著
まとめ
過去の文献を紐解いてみると、時代が進むにつれて、ビブス(ゼッケン)の使われ方に多様性が生まれてきていることがわかります。
スポーツや生活、経済といった様々な部分において世界中が繋がっている現代、ビブス(ゼッケン)の形が、今後数十年でまた大きく変わっても不思議ではないかもしれません。
後世の人が、今の私たちを見て「へ~、昔はビブス(ゼッケン)って、そんな風に使ってたんだ」と感じる場面を想像すると、ちょっと面白いですね。